業務改善や日々の業務を進めていくうえで、
仕事の早い人、遅い人
成果創出が早い人、遅い人
呼び方や捉え方は違えども、仕事の進め方、成果を出している人はどの会社や職場でもいらっしゃると思います。
その人達は単純に運がいいから・・・・という訳ではなく、少なからず
「物事の判断が早い」
「成果(アウトプット)から逆算して進めている」
場合が多いかと思います。
その共通点として自分なりの「仮説」をもって、物事を進めていることが多いと感じています。
少なからず、自分も業務改善や仕事でタスクを進めていくうえでは自分なりの問題・課題に対する要因や解決後のゴールを仮説立てて進めることでうまくいくケースが多いです。
今回はそのような仕事の早い人、成果創出が早い人に共通している「仮説思考」について解説していきたいと思います。
なお、今回の記事では「仮説思考」(内田和成さん著書)の内容や自身の経験を踏まえ、仮説思考の重要性や仮説の立て方について解説していきます。
仮説思考とは?

仮説思考とは、問題解決の初期段階で仮説を立て、その仮説を検証しながら進めていく方法です。
仮説を立てることで、問題の本質を早期に把握し、効率的に解決策を見つけ、意思決定の判断や問題解決に役立てていくことができます。
今回、参考としている著書「仮説思考」は、元ボストン・コンサルティング・グループ日本代表であり、現在は早稲田大学ビジネススクール教授として活躍する内田和成氏による著書です。
本書では、ビジネスパーソンが成果を出すために必要な思考法として「仮説思考」の重要性が説かれています。
仮説思考の本質は、「仮の答えを先に持つこと」。
つまり、問題に直面したときに、まず自分なりの仮説を立て、それが正しいかどうかを検証していくという流れです。
このアプローチにより、情報収集の方向性が明確になり、無駄な調査や分析を避けることができます。
本書では、
・仮説思考を実践するためのステップ
・仮説が間違っていた場合の対処法
・仮説を立てる際の注意点
なども丁寧に解説されています。
ただし、仮説はあくまで「仮の答え」であり、検証と修正を前提とした柔軟な姿勢が求められるという点も強調されています。
この仮説思考によって、問題解決の要因や解決策に対する自分なりの答えを先に持ち、仮説が正しいかを検証していくことで、最短コースで問題解決につなげていくことができます。
かつ、論点から脱線することなく、問題に対する深い分析を行えることにより、分析内容の質や分析結果による結論、問題解決策もより根本的かつ真因をついた内容となり、説得力のある提案や解決策の提示を行うことにもつながります。
なぜ仮説思考が必要か?
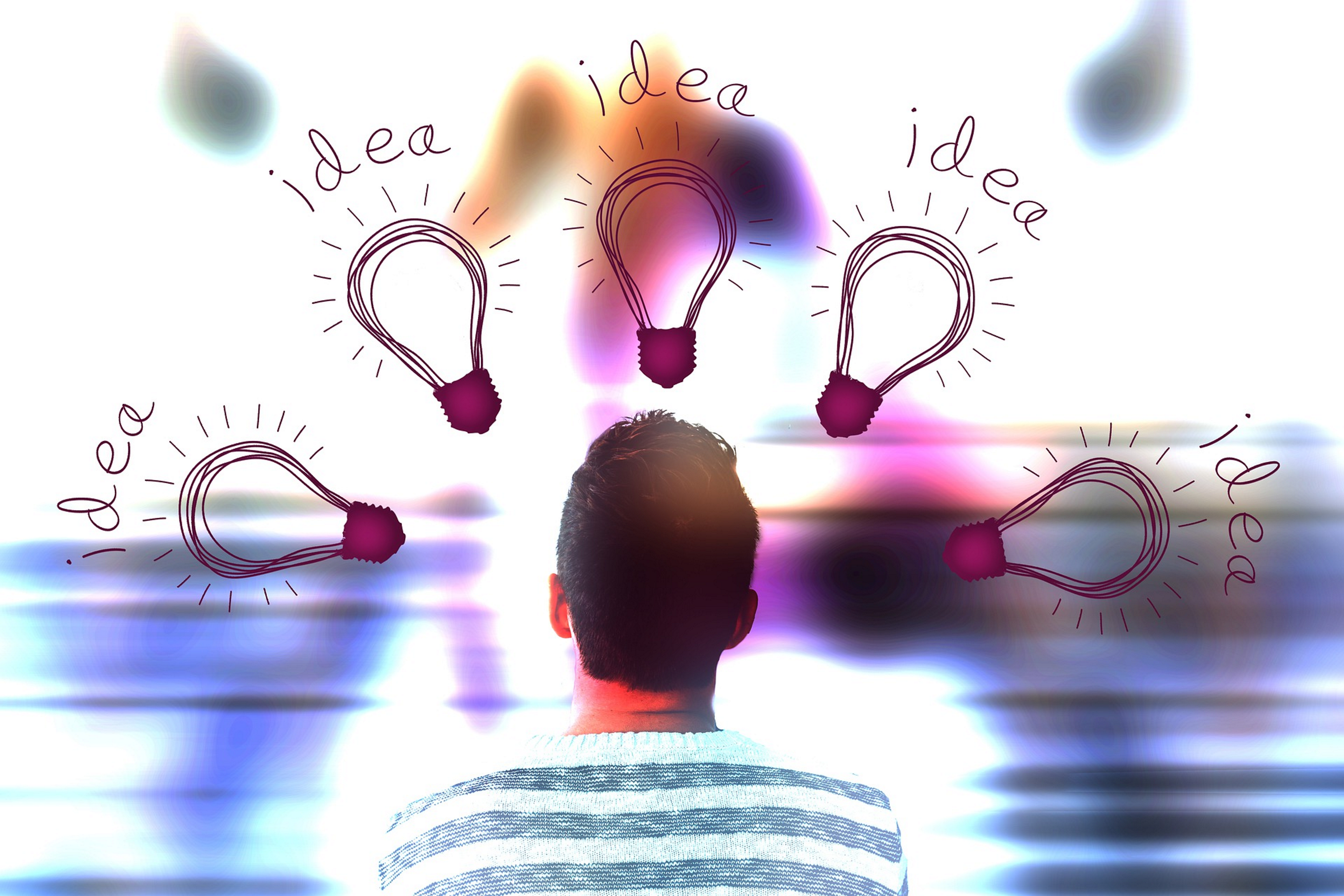
ビジネスシーンでは、よくロジカルシンキングや論理的思考について研修の機会があったりすることもあるかと思いますが、そうした中でもなぜ、仮説思考が必要となるのでしょうか?
それは、仮説思考の考え方を常に使うことで仕事の進め方が速まるだけでなく、質の高い成果や価値を生み出すことにもつながる。
現代のビジネス環境は、まさに「VUCA(不確実・不安定・複雑・曖昧)」の時代ともいわれています。
常に様々な情報にあふれ、変化は激しく、正解が見えにくい状況が日常化し、日々の業務でも定型的な業務は効率化されていきながら、より高度化した問題や課題に対する解決やビジネスモデルの構築が求められています。
そんな中で成果を出すために求められるのが、「先見性」「決断力」「実行力」という3つの力です。
この3つの力を支える思考法として「仮説思考」は非常に有効な思考法と言えます。
仮説思考とは、問題解決において「まず仮の答えを持ち、それを検証しながら進める」アプローチ。
情報を集めてから考えるのではなく、考えてから情報を集めることで、スピードと質の両方を高めることができる。
こうした、考えながら情報を集め、検証と修正を繰り返した思考とアクションを繰り返していくことで効率的かつ最適な意思決定につなげていくこともできます。
仮説思考と網羅的思考の違い
仮説思考と網羅的思考とは?
網羅的思考とは、広範囲にわたる情報を収集し、それらをつなぎ合わせて結論や問題解決策を導き出す方法です。
具体的には、問題解決のために可能な限り多くの情報を集め、その情報を基にして施策や解決策を考えるアプローチです 。
一見すると緻密に分析を行い、結論を出し、施策や解決策を考えるため、有効な思考法に思えます。
ですが、幅広い情報を様々つなぎ合わせた内容となるため、情報量が多くなり、その成果物や施策の内容は時間をかけた割には質も劣っている場合もあります。
また、時間をかけて様々な情報を加えた内容でも、結論や論点がずれていること、不明確になることで「結局、何が言いたいの?」ということを上司や顧客に説明した際に言われることにもなりかねません。
仮説思考と網羅的思考は問題解決におけるアプローチが根本的に異なります。
仮説思考はスピードと本質的な解決を重視するのに対し、網羅的思考は情報の幅広さと慎重さを重視します。
下表は、両者の違いを整理したものです。
| 比較項目 | 仮説思考 | 網羅的思考 |
| 思考の起点 | 仮の答え(仮説)からスタート | 情報収集からスタート |
| スピード | 速い(検証→修正のサイクル) | 遅い(情報収集に時間がかかる) |
| 成果の質 | 真因に近づきやすく、精度が高い | 情報過多で焦点がぼやける |
| 説得力 | 根拠を持って提案できる | 「結局何が言いたいの?」になりがち |
仮説思考は、問題の本質に迫るための「羅針盤」として機能します。一方で網羅的思考は、情報の海に溺れてしまいがちで、結論が曖昧になりやすいという弱点があります。
実際の業務を例にするとどうか
こうした仮説思考と網羅的思考を概念的に違いはありますが、実際の業務を例にするとどうでしょうか?
例えば、「小売行で販売数を増やしていくこと」、「社内業務の業務効率を改善して工数削減をする」といった問題を解決するために施策を検討するとしたとき、網羅的思考で施策を検討する場合、
・販売数を増やすために、現在の契約数や購入者の顧客属性は?
・直近の販売数は減少しているのか?増加しているのか?
・競合他社の販売数や動向は?
・全国でどの地域で販売数が多いか?
といったように、調べることやほしい情報は挙げれば切りがないほど出てきます。
この際に、販売数を増やすために網羅的に情報取得し、販売増加にに向けた施策を考え出すと、施策も相当数(多ければ10以上の施策)が思いつくかもしれません。
一見すると、施策が多くあればあるほど打ち手があるように見えます。
ですが、販売数を増加させるという問題に対して、施策の効果性や施策を進めるためのコストや優先度、制約条件も考慮し、施策も網羅的に検討し始めると、解決したい販売数増加という問題に対してアクションを起こせるまでに相当な時間がかかってしまいます。
一方で、仮説思考で「販売数を増加させる」という問題に対し、「なぜ販売数が増加しないのか?」という問題に対する要因を仮説として「顧客属性があっていない」と自分なりの答えを持った場合、「販売数が落ち込んでいる顧客層を分析する。」ことや、逆に「販売数が増加している顧客層を調べる。」といったアクションをすると思います。
この際、この「顧客属性があっていない」というのはあくまでも仮の答えなので、調べていく中で「本当に顧客属性によって販売数が増加しないのか?」ということを検証していくことになります。ここで顧客属性ではなかったとしても、それまでの取り組みが無駄になるわけではなく、次に「販売している地域に問題があるのでは?」という仮説を立てて再度検証を行っていく。
このような流れで問題に対する要因特定を進めていくことで問題の真因に近づくとともに、質の高い分析結果を残すことができます。
また、逆に顧客属性に問題があったということが検証の結果わかった場合、網羅的に情報を収集して施策検討するよりも圧倒的に時間効率も高く、販売数増加に対する施策推進や施策後の効果検証に対して時間を割くことできるため、網羅的思考で進めた場合と比べても、問題解決全体に対する時間効率や質の高さの面で仮説思考型での進め方の方がメリットが大きいです。
私自身も施策を考え、問題や課題解決に向けた施策推進や効果検証を行うことは仕事上、多々あります。
ですが、網羅的思考で情報過多となるよりも仮説思考型で要因をある程度答えをもっておき、要因の確からしさを検証していく進め方が大半です。
仮説思考のメリットと注意点
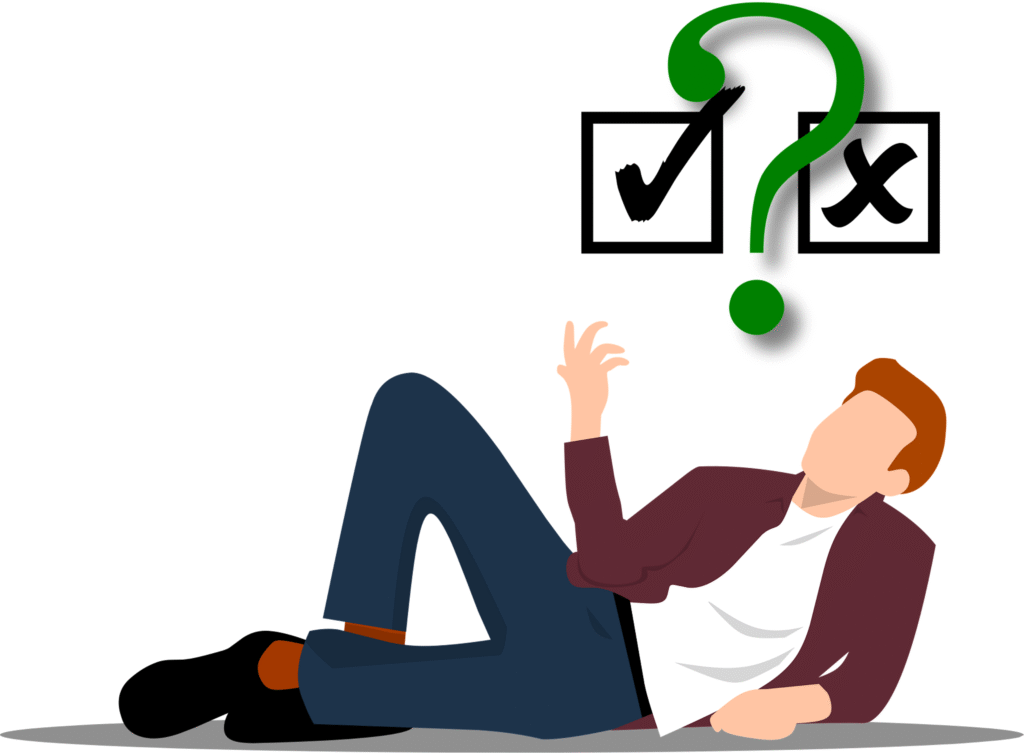
これまで、仮説思考と網羅的思考の違いについて解説してきましたが、「仮説思考」におけるメリットをもう少し深掘りするとどうなるのでしょうか?
また、仮説思考も万能ではなく、思考における注意点もあります。
それぞれについて、見ていきましょう。
仮説思考のメリット
実際に仮説思考を日々の業務でも進めている中で、下記3つのメリットがあるという実感を持っています。
提案の説得力が増す
仮説思考のポイントは「最初に自分なりの答え(仮説)を用意し、それを検証しながら精度を上げる」ことです。これによって提案資料やプレゼンにおいて、下記のような構造を組み立てることができます。
- 仮説の根拠を明示できる
自身の立てた仮説について、仮説に至る背景(購買データの傾向、競合動向、アンケート結果など)を提示できます。 - 結論がブレない
情報収集フェーズであれこれ迷うのではなく、仮説を軸に「本当に必要なデータ」を選別して集めるため、最終的な結論に一貫性が生まれます。 - 説得用の検証結果を示せる
仮説を検証した結果、〇〇%の改善効果が確認できた、あるいは別の要因が浮かび上がったといった定量的・定性的な裏付けをセットで提示できるため、相手の納得感を高められます。
問題への早期着手が可能
網羅的思考では、まずは手当たり次第に情報を集めるため、動き出すまでに膨大な時間を浪費しがちですが、仮説思考を取り入れると、下記のメリットがあります。
- 着手のハードルが下がる
「正確な答え」が見つかるまで調査し続けるのではなく、「合っていそうな答え」を先に立てることで、すぐに行動に移れます。 - 小さな検証サイクルを回せる
最初は不完全でもよい仮説を立て、短期間で検証→修正を繰り返すため、PDCAのスピードが格段にアップします。 - 重要タスクにリソースを集中できる
すべてを調べる必要がないため、限られた時間や人員を「最も影響の大きいタスク」に振り向けられます。
たとえば、新製品の販売チャネルを拡大する案件では、「ECサイト経由の購入者が増加している」という仮説を立ててすぐに「ウェブ広告を試験投入し、成果が出た場合に規模を拡大する」というアクションをとることができます。着手までの時間を圧倒的に短縮できるため、競合企業に先んじて手を打てるようになります。
効果検証の精度が高まる
仮説をベースに必要最小限のデータを集めることで、下記のように効果検証の設計がシンプルかつ精度の高いものになります。
- KPIの選定がぶれない
仮説に直結する指標(例:新規会員登録数・リピート率・客単価など)を先に定めるため、検証フェーズで何を追うべきかが明確になります。 - 比較条件のコントロールがしやすい
「本当に効果のあった要素」を切り分けるために、A/Bテストや時系列比較などの手法をピンポイントで適用でき、誤差やノイズを最小限に抑えられます。 - 改善サイクルが回りやすい
限られた指標にフォーカスして検証結果を素早く判断できるため、次の仮説に速やかにリソースを移し、試行錯誤を効率的に繰り返せます。
著書「仮説思考」では、ビジネスパーソンとしての求められる、「先見力」、「決断力」、「実行力」の3つの力のうち、「先見力」と「決断力」に仮説思考は関係性があること。(特に決断力は要因分析と施策の効果性の2面で仮説検証は外せないと思います。)
ということにつながるとの記載があります。特に「大局観をもって仕事ができる。」という点においてはイメージしづらいかもしれないですが、多くの関係者と仕事を進めていくような場合はとても重要な点であると感じています。
なぜなら、仮説思考を持つことで自身のおかれた領域だけでなく、視座を高め、俯瞰して前後工程への影響や経営視点でのメリット・デメリット、業務工数といった全体感で仕事見ることができるようになるからです。
一見すると、「情報洪水になるのでは?」「網羅的な考えに近くないか?」というような見方もできますが、「情報を選別し、捨てていく」ための判断基準として全体感で仮説を立てていくことになるため、最終的には情報を必要最小限に絞り込むことができるようになります。
仮説思考の注意点と落とし穴
もちろん、万能に思える仮説思考にも注意すべき点があります。
仮説に固執してしまうと、「思い込み」に陥るリスクがあります。
仮説はあくまで「仮の答え」であり、検証と修正を前提とした柔軟な姿勢が必要です。
また、仮説に頼りすぎると、客観的なデータを軽視してしまう危険性もあります。
仮説を立てた後は、必ずデータや事実に基づいて検証することが重要です。
さらに、チームで仕事を進める場合には、仮説を共有し、対話を通じて合意形成を図ることが求められます。
仮説思考は個人の力を高める一方で、チームとの連携にも配慮が必要です。
こうした3つの注意点に気を付けることで、仮説思考で陥りがちな落とし穴にはまることなく、思考することが可能になります。
仮説思考を身に着けるためのアクション

ここまで解説してきた仮説思考ですが、「知っている」だけでは仕事は変わりません。
実際に日々の仕事や生活の中で使ってみることで、その効果を実感できます。
実際に、仮説思考を実務に落とし込むための具体的なアクションとして、下記の流れが参考になるかと思います。
1. 日々の業務で「仮説」を意識する
・問題や課題に対し、「この課題の原因は○○では?」と仮説を立て、施策の立案や検証を行っていくことで、自身の仮説の精度を上げていくことが大切です。
2. 仮説を言語化する
思考していると、頭の中で物事を様々考えがちになってしまいますが、どんどん頭の中で思考していくとだんだんと物事のつながりやせっかく考えた仮説が不明確なものになってしまうこともあります。自身の仮説をある程度形にしたら紙に書き出すなど、言語化することで仮説を明確化すること。そして仮説が正しかったか振り返ることにも役立ちます。
3. 検証と修正を前提に動く
初めから論点をついた仮説や正解にたどり着く仮説を導き出すことは至難の業です。仮説思考も日々日々の仮説立てと検証、修正を繰り返していくことでその精度も高まっていきます。
そのためには、初めから精度の高い仮説を求めるのではなく、多少荒くても自分で立てた仮説を検証し、修正や再度仮説を立て直すことを繰り返し、仮説の立て方や思考の癖を振り返る習慣を持つことが大切です。
4. 学びを継続する
とはいえ、独学で仮説思考を身に着けていくことはなかなか難しくもあります。そのため、書籍や講座で仮説思考の型を学び、実務で試すことで、思考力と実行力の両方を鍛え、自分の仮説が当たった/外れた事例を記録し、再現性のある思考パターンを構築していくことが重要です。
効率的に学んでいくためには?~書籍やUdemyを活用しよう~
上記で解説したように、独学で仮説思考を学ぼうとしても思った通りに仮説立てすることができなかったり、いざ仮説を立てて検証しても仮説通りでなかったときにどうすればいいか・・・・と実践しても障壁にあたることもあると思います。
そうした時に、助けとなるのが書籍や動画コンテンツなどの学習に使えるコンテンツです。
特に書籍であれば、今回の記事の参考にもなっている、
「仮説思考 BCG流 問題発見・解決の発想法 」(内田和成氏 著書)
が大変参考になります。
≪仮説思考 BCG流 問題発見・解決の発想法≫
また、動画コンテンツであれば、オンライン学習プラットフォーム「Udemy」がオススメです。
他の記事でも紹介しておりますが、私自身、Udemyを利用して、
・ハンズオン形式で手を動かしながら学ぶことができる。
・動画のため、再生速度を調節しながら時短できる(1.5倍速~2倍速で視聴していました。)
・ポイントを絞って、繰り返し視聴で学習できる。
といった良かった点がありました。
Udemyではよくセールをしているため、セール期間中であれば90%以上割引(1動画1,200円~1,800円程度)で購入できます。
下記の講座は、仮説思考を含む思考力を鍛えるのに最適な講座だと思います!
定番!正解のない問いに答えを出す問題解決スキル:ゼロから学ぶ仮説思考&ロジカルシンキング
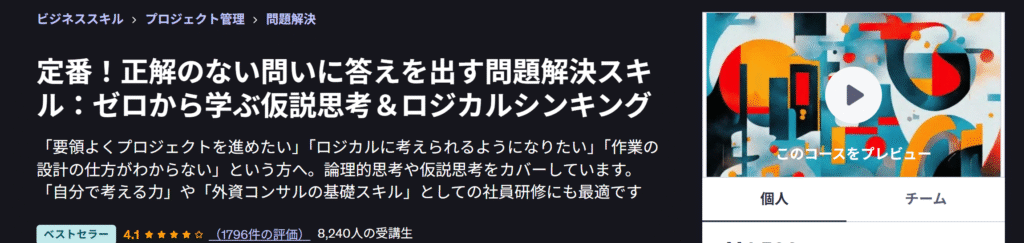
【明日から実践!】短時間と高品質を両立させる問題解決入門 ~仮説思考編
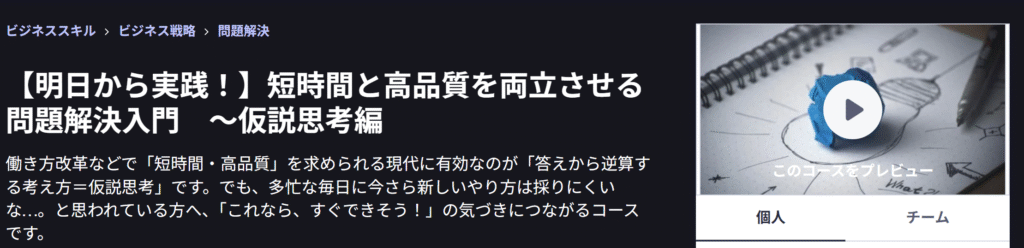
【抜粋版】短時間でポイント速習!仮説思考力の高め方 ~まずは仮説思考のポイントを理解したい方向けのショート講座
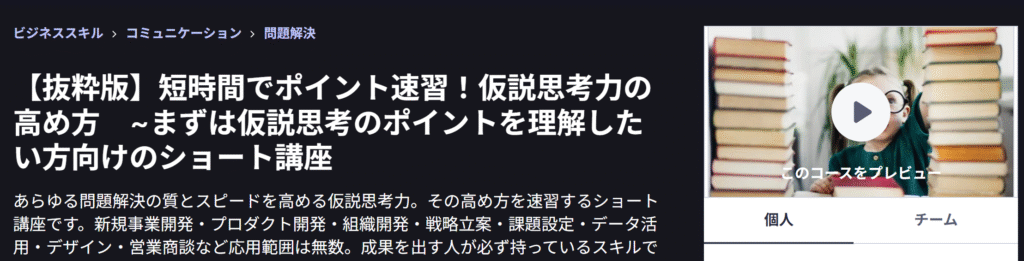
まとめ

仮説思考は情報過多の時代において「何を信じ、どう動くか」を決めるための羅針盤として働きます。仮の答えを持って前に進むことで、迷う時間を減らし、成果に近づくことができます。
また、下記のようなメリットを享受することにもつながります。
・情報収集の方向性が定まる
・意思決定のスピードが上がる
・問題の本質に迫れる
・チームの認識を揃えられる
重要なのは「仮説は間違っていてもよい」という前提。検証と修正を通じて、より良い答えに近づくことができるのです。
そのためには、初めは間違ってもよいのでまずは自分なりの仮説を立てて、検証し、正しさを判断する。これを繰り返していくことで仮説の精度を高めていき、自身の思考力の強化や問題解決の能力を向上させていきましょう。
今回の記事から、
・日々の業務で仮説思考を取り入れてみよう。
・仮説思考を学んでみよう。
と思ってもらえると幸いです!
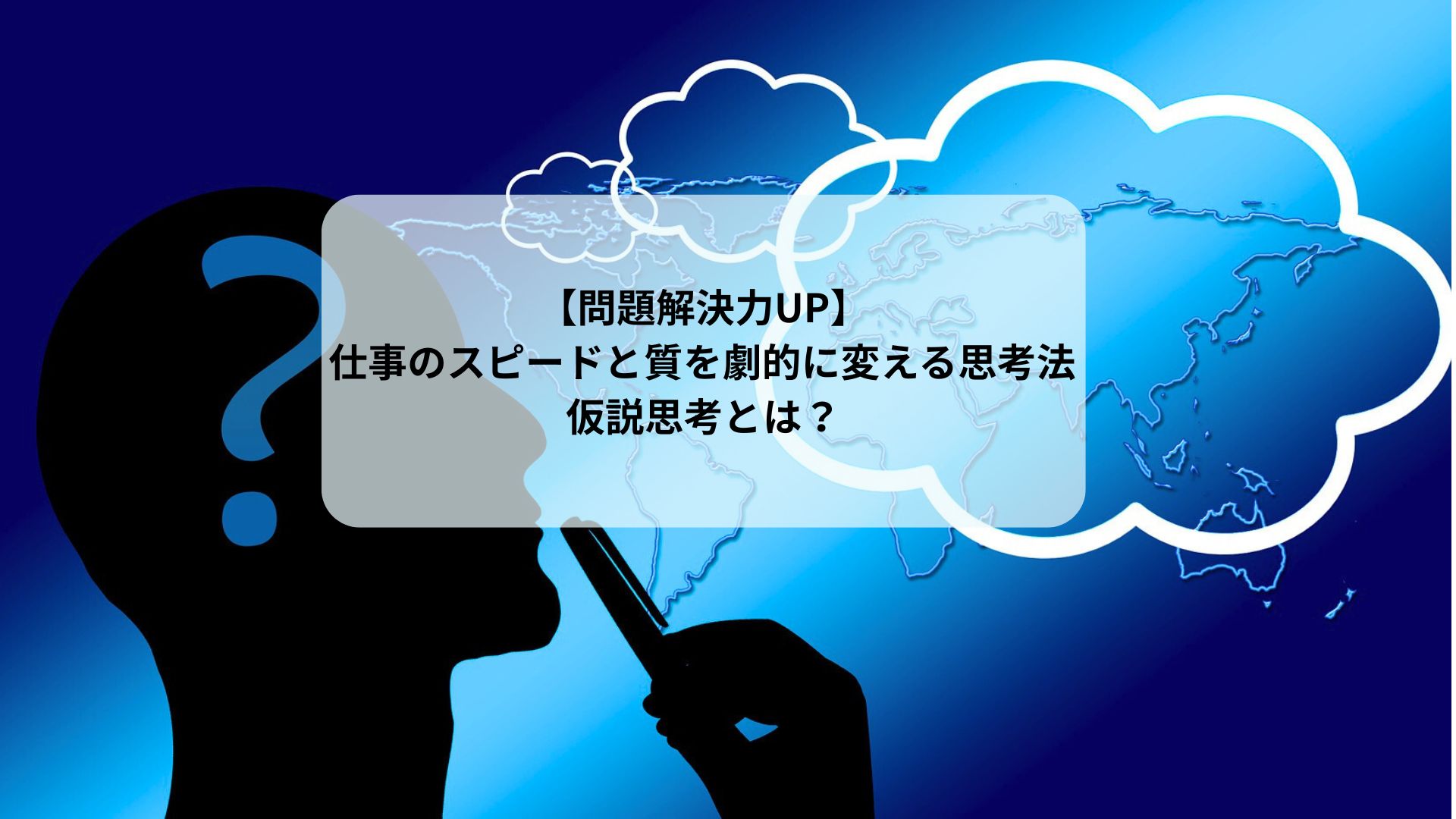


コメント